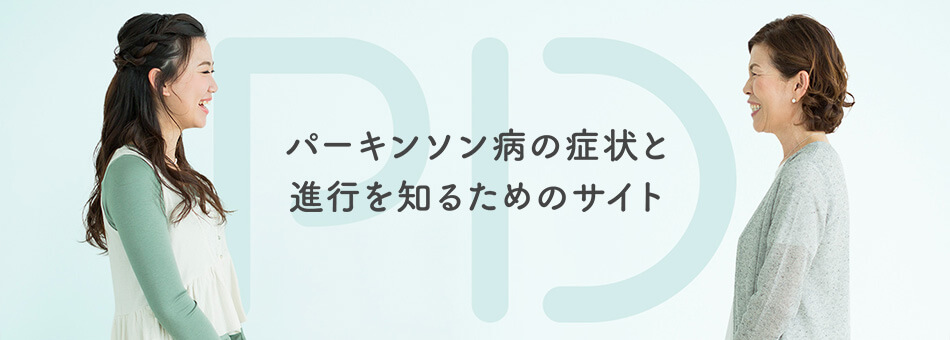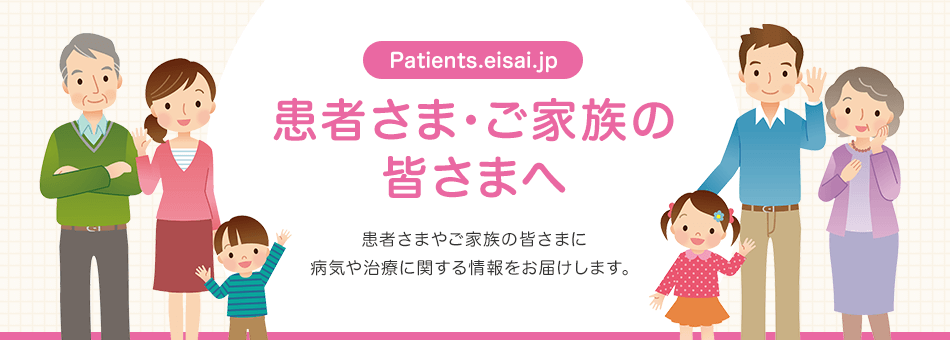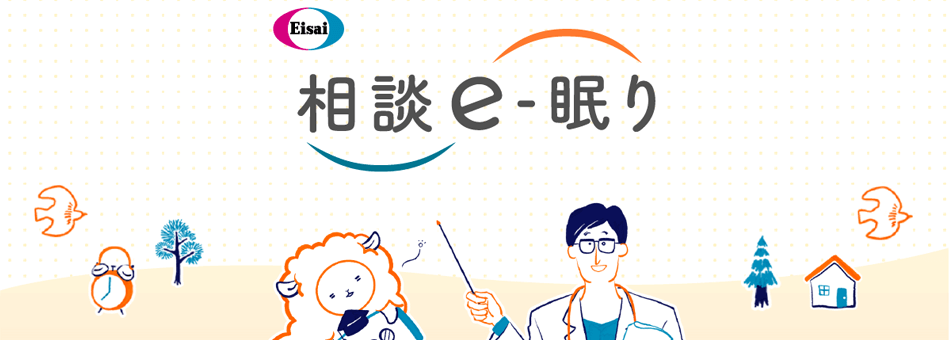Eisai Patients.eisai.jp 患者さま・ご家族の皆さまへ
更新情報
- 2023/07/24「病気や治療の情報サイト」に「不眠症」を追加しました。
- 2022/03/08BreCare Garden(ブレケア ガーデン)は、女性のがんサバイバーのサイト「Ladyluna Garden(レディルナ ガーデン)」としてリニューアルいたしました。
- 2020/03/19「病気や治療の情報サイト」に「パーキンソン病」を追加しました。
- 2019/03/28「病気や治療の情報サイト」に「肝疾患」を追加しました。
病気や治療の情報サイト
患者さまやご家族の皆さまに病気や治療に役立つ情報をご紹介します。
-
認知症
相談e-65 そうだんイーローゴ
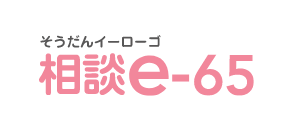
相談e-65 そうだんイーローゴ
認知症の種類や原因、治療に関する情報や、
介護方法・体験談など認知症と歩む皆様に
向けた情報を掲載しています。※相談e-65は、エーザイグループのTheoria technologies株式会社が運営する認知症情報サイトです。
-
不眠症
相談e-眠り そうだんイーネムリ

相談e-眠り そうだんイーネムリ
不眠症の種類や原因、治療に関する情報など
睡眠に関して悩みを抱える皆様に
向けた情報を掲載しています。 -
パーキンソン病
PDネット

PDネット
パーキンソン病の症状と進行を
知るためのサイトです。 -
女性のがん
Ladyluna Garden
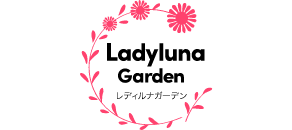
Ladyluna Garden
私らしい暮らしを楽しむ
女性のがんサバイバーのサイトです。 -
肝疾患
肝疾患サポートサイト
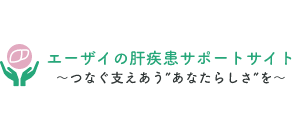
肝疾患サポートサイト
つなぐ、支え合う“あなたらしさ”を。
肝疾患の症状や体験談、相談窓口を紹介するサイトです。 -
てんかん
epiサポ

epiサポ
てんかんを正しく知り、
てんかんと暮らすためのアドバイスを
紹介したサイトです。 -
甲状腺がん
甲状腺がん.hhc
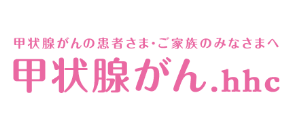
甲状腺がん.hhc
甲状腺がんの症状や治療法の情報を
紹介します。おしゃれなスカーフの
巻き方も紹介しています。 -
腰痛
新しい腰みがき

新しい腰みがき
高齢の方にもできる
腰痛体操「腰みがき」で腰痛を
予防をしましょう。